アレルギー性鼻炎とは
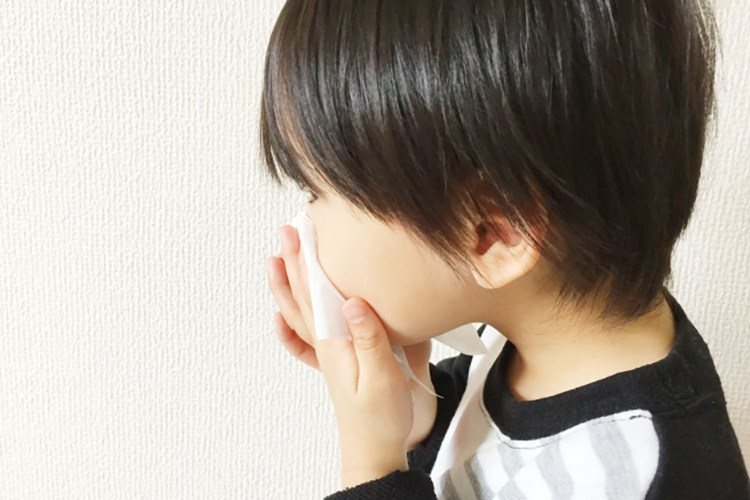
アレルギー性鼻炎は、ハウスダスト、花粉、ペットの毛などのアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)に対し、体が過剰に反応して鼻の粘膜に炎症を起こす病気です。
近年、発症年齢の低下が進み、子どものアレルギー性鼻炎も多く見られるようになっています。
大人と同様に、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどの症状が現れますが、子どもは症状をうまく表現できない場合も多く、親が注意深く観察する必要があります。また、大人と比べて、症状が重症化しやすい傾向や、喘息などの他のアレルギー疾患を併発する可能性も高いため、早期発見と適切な治療が重要です。
症状の持続期間によって、通年性アレルギー性鼻炎(一年中症状がある)と季節性アレルギー性鼻炎(特定の季節に症状が出る)に分類されます。
アレルギー性鼻炎は、命にかかわるような重篤な病気ではありませんが、鼻水や鼻のかゆみのため集中できず、学業や日常生活に大きな影響を与える可能性があります。
アレルギー性鼻炎の原因
アレルギー性鼻炎の原因は、特定のアレルゲンに対する体の過剰な免疫反応です。子どもの免疫系はまだ発達途上であるため、大人よりもアレルゲンに過敏に反応しやすい傾向があります。
主なアレルゲンとしては以下が挙げられます。
- ハウスダスト
- ダニの死骸、フン、カビの胞子など。特に、カーペット、布団、ぬいぐるみなどに多く潜んでいます。
子どもの生活空間におけるダニ対策は特に重要です。 - 花粉
- スギ、ヒノキ、ブタクサなど。季節性アレルギー性鼻炎の主な原因です。
- ペット
- 犬や猫などの動物のフケ、唾液など。
ペットを飼っている家庭では、アレルゲンとなる物質を減らす対策が不可欠です。 - 食品
- 特定の食品がアレルゲンとなる場合もあります。食物アレルギーとの関連も注意深く観察する必要があります。
- カビ
- 湿気の多い場所によく発生し、胞子がアレルゲンとなります。
浴室やクローゼットなど、子どもの生活空間におけるカビ対策も重要です。
アレルギー性鼻炎の症状
小児のアレルギー性鼻炎の症状は、大人と同様にくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどが挙げられますが、言葉で症状を伝えられない乳幼児期には、以下の様なサインに注意が必要です。
- 鼻が痒くて何度も触る、こするなどの行動、鼻血が出ることが多い。
- 鼻づまりによる呼吸困難で眠りが浅い、夜泣きをする。
- 鼻づまりや口呼吸により、十分に食事ができない。
- 症状による不快感から、普段より不機嫌になったり、イライラしたりする。
これらの症状に加え、大人と同様に、目の痒み、充血、涙目などのアレルギー性結膜炎を伴うことも多く見られます。症状が重症の場合、集中力の低下や学習への支障も懸念されます。また、感冒薬と一緒に抗ヒスタミン薬(抗アレルギー薬)を服用している間、鼻汁や鼻の痒みが治まった場合もアレルギー性鼻炎の可能性があります。
アレルギー性鼻炎の治療
アレルギー性鼻炎の治療は、症状の軽減と生活の質の向上を目指します。治療法は、年齢、症状の重症度、アレルゲンなどを考慮して判断します。
薬物療法
抗ヒスタミン薬、ステロイド点鼻薬などが使用されます。症状に応じて、点眼薬、抗アレルギー薬の内服薬などが用いられることもあります。「初期療法」といって、花粉飛散2週間ほど前から薬物療法を開始・飛散終了時期まで継続することで、花粉飛散後から薬物療法を開始した場合より効果が高いといわれています。
舌下免疫療法
アレルゲンに対する免疫を徐々に弱めていく治療法で、効果が期待できる一方、治療期間が3~5年と長期に渡るため、導入には時間と忍耐が必要です。
治療は、1日に1回、治療薬を舌の下に保持した後に飲み込みます。アレルギー反応がないか確認するために初回の服用はクリニックで行いますが、2日目からは自宅でも可能です。
スギ花粉症またはダニアレルギー性鼻炎と確定診断された方が治療を受けることができ、5歳以上で、薬を舌の下に1分間置くことができれば治療が可能です。
スギ花粉症の場合は、スギ花粉の飛散がない6~12月の間から開始できます。(1~5月はアナフィラキシーショックの可能性があるため治療を開始できません。)
また、治療と並行して大人以上に徹底したアレルゲン対策が重要です。
ハウスダスト対策として、こまめな掃除、布団の乾燥、ダニ対策、ペットとの接触制限、湿度の管理などが必要です。
小児のアレルギー性鼻炎は、放置すると喘息などの他のアレルギー疾患を併発するリスクが高まるため、早期の受診と適切な治療が重要です。
風邪を繰り返していると思っていたら実はアレルギー性鼻炎だったということもありますので、気になる症状がある場合は早めに受診することをおすすめします。

